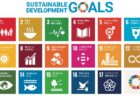社会問題を解決するための様々な取り組みやコンセプトを一覧にしてまとめています。SDGsやパリ協定、ESGといった世界規模の取り組みから、関係人口や地域通貨といった地域の取り組みまで、あらゆる種類の題材を紹介しています。
目次
- 社会問題解決に向けた取り組み・コンセプト一覧
- RE100
- アップサイクル
- ESG(イー・エス・ジー)
- ヴィーガンレザー
- エコロジカル・フットプリント
- エシカル消費
- SDGs(エス・ディー・ジーズ)
- オープンイノベーション
- カーボンニュートラル
- カーボンプライシング
- 関係人口(かんけいじんこう)
- クラウドファンディング
- 幸福度
- サーキュラーエコノミー
- サードプレイス
- サステナブルコーヒー
- サステナブルフード
- サステナブルファッション
- スマートシティ
- スマートヘルスケア(スマート医療)
- 生態系サービス
- ソーシャルグッド
- ソーシャルビジネス
- ダイベストメント
- 地域通貨
- バイオ燃料
- バイオプラスチック
- パリ協定
- BOP(ビー・オー・ピー)
- ファッション協定(THE FASHION PACT)
- フェアトレード
- ブルーエコノミー
- ブルーカーボン
- ベーシックインカム
- MaaS(モビリティ・アズ・ア・サービス)
- リカレント教育(リスキリング)
- リバース・イノベーション(Reverse innovation)
- おわりに|社会問題の解決策 様々な取り組みやコンセプト一覧
社会問題解決に向けた取り組み・コンセプト一覧
RE100
“Renewable Energy 100%”の頭文字をとってRE100と名付けられた、The Climate GroupとCDPによって運営される企業の自然エネルギー100%を推進する国際ビジネスイニシアティブです。
加盟企業は事業活動で使用するエネルギーを100%再生可能エネルギーに転換する期限を設けた計画を立てて事務局の承認を受けることになっています。
日本では、2009年に発足したJCLP(日本気候リーダーズ・パートナーシップ)が窓口となっており、2021年7月現在、JCLPに加盟する169社のうち、リコー、イオン、大和ハウスなど58社がRE100に参加しています。
アップサイクル
アップサイクル(upcycle)は、不用品を新しい価値をもった別のものに生まれ変わらせる「アップサイクリング」というプロセスを意味します。
広義にはリサイクルの一種ですが、製品を別の原料や素材に変換することで価値や質が下がってしまう「ダウンサイクル」と異なり、「製品」に変換することで価値や質を高めるという意味で「アップサイクル」と呼びます。
元の製品の特徴を生かしてより良いものに作り変えることで価値を高めようとする考えのため、創造的再利用とも呼ばれています。デザインが重要な役割を果たすため、ファッションやデザインなどのアーティスト分野との連携が進んでいます。
ESG(イー・エス・ジー)
ESGとは環境(Environment)、社会(Social)、企業統治(Governance)という3つの言葉の頭文字からなる略語です。
投資をする際に、利益やキャッシュフローなどの財務情報に加えて、非財務情報としてESGの要素を重視するという形で用いられるため、ESG投資とも呼ばれます。
2006年に国連環境計画・金融イニシアティブが主導して作成した「国連責任投資原則(PRI)」のなかで、投資分析と意思決定のプロセスにESGの課題を組み込む等として明記されたことがきっかけとなりました。
2018年には世界のESG投資残高は30.7兆ドルに達しています。
ヴィーガンレザー
ヴィーガンレザーは動物の皮を使用せずに革の見た目・質感を再現した素材で、主に基布に合成樹脂を塗り重ねることで作られます。プラスチックなどの合成皮革やコルクなどの天然素材など、ヴィーガンレザーの製造に使用できるさまざまな素材があります。
なかでも植物由来のヴィーガンレザーは、環境に配慮された素材であるということから注目が高まっています。
エコロジカル・フットプリント
エコロジカル・フットプリント(Ecological Footprint)とは、直訳すると「環境上の足跡」となりますが、人間の活動が環境に与える負荷を表す指標です。
1992年にカナダのブリティッシュコロンビア大学のウィリアム・リース氏によって提唱された概念です。
その定義は「ある特定の地域の経済活動、またはある特定の物質水準の生活を営む人々の消費活動を永続的に支えるために必要とされる生産可能な土地および水域面積の合計」であり、これによって、地域によって、どれくらい適正規模を超えた経済活動をしているかがわかります。
地球を持続可能にするためには、地球1個分の暮らしをする必要があると言われたりしますが、その計算の元になる概念であり指標です。
エシカル消費
エシカル消費(Ethical Consumption)とは、私たち消費者が購入する商品が「いつ・どこで・誰がどうやって作ったのか?」という生産・流通の背景にまで気を配って、社会問題の解決に貢献できる商品を購入しましょう」という活動です。
我々が何気なく購入している商品はもしかしたら貧困国の子ども達を低賃金・⻑時間働かせて作ったものかもしれません。そうした背景を知り、搾取を助長しないものを買うことは社会問題の解決にもつながります。
国連が掲げるSDGs(持続可能な開発目標)に「つくる責任、つかう責任」という項目があります。エシカル消費を実践することで、そうした責任を果たすことにつながります。
また、貧困をなくす、人や国の不平等をなくす、気候変動に具体的な対策を、海の豊かさや陸の豊かさなどを守る、といった目標を解決していくために、エシカル消費はとても有効です。
SDGs(エス・ディー・ジーズ)
“Sustainable Development Goals”略してSDGs(エス・ディー・ジーズ)と呼びます。日本語では持続可能な開発目標と訳しています。
2030年に向けた具体的行動指針で、グローバル目標として17の分野別目標と169項目のターゲット(達成基準)から構成されています。
17の目標は、”貧困をなくそう”、”飢餓をなくそう”といった、従来型の開発途上国向けで公的機関が主体となって取り組むものだけでなく、”働きがいも経済成長も””エネルギーをみんなにそしてクリーンに”といったように、先進国や民間企業も取り組むべき目標が組み入れられています。
日本では、これまでは大企業を中心にCSR的なSDGsへの取り組みがなされてきましたが、一般人にも認知や関心度が高まりつつあるため、中小企業やスタートアップにとってもビジネスチャンスとなることが予想されています。
オープンイノベーション
2003年にアメリカのハーバード大学経営大学院の教授ヘンリー・チェスブロウが著書で発表した概念で、企業外部の技術やアイデアを積極的に取り入れてイノベーションを展開するという方法論です。
また、それ以前の、自社だけで研究開発を行う自前主義や垂直統合型のイノベーションのモデルを「クローズドイノベーション」と名付けました。
オープンイノベーションで定義されているイノベーションは、技術分野に限定されるものではなく、人事制度や社内システムまで多岐に及びます。また、イノベーションは分野が異なる技術やアイデアの融合であるほど、難易度は高いものの、より革新的になります。
カーボンニュートラル
環境化学用語で、ライフサイクルの中で炭素の排出量と吸収量がプラスマイナスゼロの状態をカーボンニュートラルと定義しています。
2020年10月26日に、菅総理大臣が所信表明演説で「2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする。すなわち2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指す」と宣言して以来、カーボンニュートラルという言葉を耳にすることが多くなりました。
菅総理大臣が唱えるカーボンニュートラルでは、国家全体の排出量に対して、カーボンオフセットなども組み合わせて全体でプラスマイナスゼロにすると定義しています。
カーボンプライシング
カーボンプライシング(略称;CP)とは、「二酸化炭素に価格をつけて、排出した量に応じて企業にお金を負担してもらう」という意味となります。
地球温暖化の主な原因と見なされている二酸化炭素の排出を抑制するために生まれた仕組みです。
カーボンニュートラルを達成するための仕組みとして、各国政府主導による「カーボンプライシング、企業が独自に導入する「インターナルカーボンプライシング」といった取り組みが急速に進みつつあります。
関係人口(かんけいじんこう)
関係人口とは”地域と多様に関わる人々”を指す言葉です。
地域を行き来する人や、地域にルーツがあるが別の地域に住んでる人、過去に勤務・居住していた人、一定期間滞在していた人など、その地域に所縁(ゆかり)がある人々が「関係人口」に該当します。
生まれた時からずっと住んでいる人や、外から移住してきたような「定住人口」と、観光に訪れる一過性の「交流人口」の中間にあたる概念といえるでしょう。
地方は人口減少や高齢化によって、地域づくりの担い手不足という課題に直面しています。その地域のことを自分ごととして考え、未来に向けて良い変化を生み出す人材の候補として「関係人口」と呼ばれる地域外の人材が期待されています。
クラウドファンディング
クラウドファンディングは「群衆(crowd)」と「資金調達(funding)」の組み合わせからなる造語です。
不特定多数の人がインターネットを介して、他の人々や組織が立ち上げたプロジェクトに対して、財源の提供や協力などを行うことを意味しています。
世界のクラウドファンディング市場規模は2015年度で約344億ドルとされ、2020年までに900億ドル規模に成長すると推定されています(世界銀行)。日本のクラウドファンディング市場規模は、2017年度は1,700億5,800万円、2018年度は2,000億円を超えると予想されています(矢野経済研究所調べ)。
資金提供者に対するリターン(見返り)の形態によって、以下のタイプに分類されます。
- 「寄付型」…金銭的リターンがない
- 「投資型」…金銭リターンがある
- 「購入型」…プロジェクトが提供する商品やサービスを購入することで支援する
幸福度
国民総幸福量(Gross National Happiness – 略称:GNH)という指標があります。
経済的側面から物質的な豊かさを測る指標である国内総生産(Gross Domestic Product – 略称:GDP)に対し、精神面での豊かさを測る指標として、1972年にブータン王国の提唱で、ブータン王国で初めて調査されました。
1990年代からの急速な国際化に伴って、ブータンで当たり前であった価値観を改めてシステム化する必要性を感じて開発。現在のブータン政府は国民総幸福量の増加が政策の中心となっています。
国連も2012年以降、150以上の国や地域を対象とした「World Happiness Report(世界幸福度調査)」を発表するようになりました。
この調査における幸福度とは、自分の幸福度が0から10のどの段階にあるかを答える世論調査によって得られた数値の平均値を基に、GDPや健康寿命を含む複数の説明変数を用いて分析しています。
2020年はフィンランドが3年連続で最も幸福度の高い国となり、日本は62位で2019年の58位から4ランクダウンという結果になりました。
日本は2010年代前半は40位台をキープしていましたが、2020年には過去最低を記録しており、年々低下傾向にあります。
その他の幸福に関する世界的な調査としては、ミシガン大学を中心に行われてきた「世界価値調査(World Values Survey)」や、イギリスのレスター大学の「世界幸福地図(World Map of Happiness)」などがあります。
また、フランスのサルコジ大統領が、ノーベル経済学賞を受賞したスティグリッツやアマルティア・センといった経済学者に委託してGDPに代わる指標に関する報告書をまとめています。
サーキュラーエコノミー
“Circular economy(サーキュラーエコノミー)”とは日本語では「循環型経済」と訳します。
製品を生産し、使用後には廃棄してしまって終わりという”直線”ではなく、リサイクルやリユースなどで再生することによって”円形状”に循環する経済の仕組みのことを言います。
世界的なコンサルティング会社のアクセンチュアによれば、サーキュラーエコノミーによる経済効果は2030年までに4.5兆米ドル(約470兆円)に達するとのことです。
サードプレイス
サードプレイスとは「居心地の良い第3の場所」を指します。カフェ、クラブ、公園などがあります。
アメリカの社会学者であるレイ・オルデンバーグは、
- “第1の場”をその人の自宅で生活を営む場所
- “第2の場”は職場や学校等の、その人が最も長く時間を過ごす場所
- “第3の場”はコミュニティライフの“アンカー”ともなるべきところで、より創造的な交流が生まれる場所
であると言っています。そして、オルデンバーグが定義するサードプレイスには、8つの特徴があります。
- 中立
- 平等
- 会話が主たる活動
- アクセスしやすさと設備
- 常連・会員(新参者にも優しい)
- 控えめな態度・姿勢
- 機嫌がよくなる
- 第2の我が家のよう
サステナブルコーヒー
サステナブルコーヒーとは、未来のことを考えて、自然環境や人々の生活を良い状態にたもつことを目指して生産・流通されたコーヒーの総称です。
コーヒーに関する様々な問題を克服して、コーヒーをサステナブル(持続可能)にすることを目指す国際的なイニシアティブであるSCC(サステナブル・コーヒー・チャレンジ)は、コンサベーション・インターナショナルとスターバックスが中心になって設立され、今では160以上の組織や政府が加盟しています。
サステナブルフード
”Sustainable Food”(サステナブルフード)とは「食が世界の持続可能性にもたらす負の影響を軽減するために、人や社会の健康と地球環境に配慮して作りだす食品」を意味しています。
食は巨大な産業であり、それに伴って「健康」「環境」「経済」の観点で大きな負の影響を生じさせてもいます。そのような状況を変えるためにサステナブルフードの普及が求められています。
サステナブルファッション
英語で”Sustainable fashion”と綴ります。
「衣服の生産から着用、廃棄に至るプロセスにおいて将来にわたり持続可能であることを目指し、生態系を含む地球環境や関わる人・社会に配慮した取り組み」を意味しています。
スマートシティ
スマートシティの定義は発信主体によって異なる部分もあり、明快に確立はされていません。例えば、
- 国土交通省
都市の抱える諸課題に対して、ICT等の新技術を活用しつつ、マネジメント(計画、整備、管理・運営等)が行われ、全体最適化が図られる持続可能な都市または地区- 経済産業省
家庭やビル、交通システムをITネットワークでつなげ、地域でエネルギーを有効活用する次世代の社会システム- 総務省
都市や地域の機能やサービスを効率化・高度化し、生活の利便性や快適性を向上させるとともに、人々が安心・安全に暮らせる街
というように、国土交通省・経済産業省、総務省でそれぞれ定義が異なります。ただ、先端技術を駆使して都市の課題解決に注力するという方向性は共通しています。
スマートヘルスケア(スマート医療)
膨れ上がる社会保障費抑制のために、健康寿命を延ばすこと、即ち、病気予防を目的とするヘルスケア領域の取り組みが重要となっています。
NRIの予測では、生活者の日常の活動に関する情報やバイタルサイン(体温、脈拍などの生命徴候)を収集・分析してQOLの改善につなげていくヘルステック(HealthTech)の国内市場規模は、2025年度には2,254億円となることが予想されています。
スマートヘルスケアに用いられる技術には、以下のようなものがあります。
- ウェアラブル端末(スマートウォッチ・スマート衣料等)
- IoT
- AI(人工知能)
- ビッグデータ
- 医療クラウド
- VR・AR(仮想現実・拡張現実)
生態系サービス
人類は生物多様性を基盤とする生態系から得られる恵みによって支えられていますが、生物・生態系に由来するもので人類の利益になる機能のことを「生態系サービス」と呼びます。
1997年に雑誌『Nature』で発表された論文によると、その経済的価値は年平均33兆ドルと見積もられています。
ソーシャルグッド
「ソーシャルグッド」とは、社会に良いな影響を与えるような活動や製品、サービスの総称を指します。
ミレニアル世代やジェネーションZ世代を中心に、これまでの大量生産・大量消費型の資本主義には明るい未来はないと考え、サステナビリティー(持続可能性)を重視したソーシャルグッドな考え方や行動を選択する人が増えてきています。
ソーシャルビジネス
グラミン銀行を設立し、マイクロクレジットによる貧困撲滅の取り組み等に対する功績から2006年にノーベル平和賞を受賞したバングラデシュのムハマド・ユヌス博士が、ノーベル平和賞の受賞式典で資本主義経済の構造に根本的な変化をもたらすことができる新しい概念として、はじめてソーシャルビジネスという言葉を使いました。
ユヌス博士による、グラミンのソーシャル・ビジネスの7つの原則は以下の通りです(原文のメモを見ると6つの原則となっていて、最後の7つ目が付け足されています)。
- ソーシャルビジネスの目的は、利益の最大化ではなく、貧困、教育、環境等の社会問題を解決すること。
- 経済的な持続可能性を実現すること。
- 投資家は投資額までは回収し、それを上回る配当は受けないこと。
- 投資の元本回収以降に生じた利益は、社員の福利厚生の充実やさらなるソーシャルビジネス、自社に再投資されること。
- ジェンダーと環境に配慮すること。
- 雇用する社員にとってよい労働環境を保つこと。
- 楽しみながら。
ダイベストメント
ダイベストメント(英語:divestment)は、投資(英語:Investment)の対義語で、既に投資している株・債券等の金融資産を引き揚げることを意味します。
投資判断に際し、ESG(環境・社会・企業統治)を重視する考え方が広がっており、石油・石炭などのGHGを排出する事業資産は将来使用できなくなる可能性があると考え、化石燃料や石炭関連の事業への投融資から撤退する動きが始まっています。
また、そうした環境側面に加えて、健康面から社会に悪い影響を及ぼすタバコ産業から投資を引き揚げるなどのダイベストメントが進んでいます。
地域通貨
法定通貨(=お金)ではないものの、ある目的や地域のコミュニティー内などで、法定貨幣と同等の価値あるいは全く異なる価値があるものとして発行され使用される貨幣のことを指します。
経済学者の西部(にしべ) 氏によれば、地域通貨は以下のような特徴を持っています。
- 特定の地域内(市町村など)、あるいはコミュニティ(商店街、町内会、NPO)などの中においてのみ流通する。
- 市民ないし市民団体(商店街やNPOなど)により発行される。
- 無利子またはマイナス利子である。
- 人と人をつなぎ相互交流を深めるリングとしての役割を持つ。
- 価値観やある特定の関心事項を共有し、それを伝えていくメディアとしての側面を持つ。
- 原則的に法定通貨とは交換できない。
バイオ燃料
バイオ燃料とは生物体(バイオ)から作る燃料のことを意味しています。
2025年のカーボンニュートラル実現に向けて、温室効果ガス排出の主要因となっている化石燃料の代替として注目が高まっています。
日本国内では、2021年6月にユーグレナ社がバイオジェット燃料を導入したフライトを成功させたことがニュースになりました。
バイオプラスチック
「バイオプラスチック」(英語:bioplastic)とは、「バイオマスを原料としたプラスチック」と「生分解性を持つプラスチック」の総称です。
気候変動や海洋汚染対策として注目されており、石油を原料とするプラスチックから、バイオプラスチックに置き換えられていくことが期待されます。
パリ協定
2015年12月12日にパリで開催されたCOP21で196のUNFCCCの締約国(全196ヵ国)によって採択され、2016年11月4日に発効された、気候変動に関する国際条約です。
「産業革命以前のレベルと比較して、世界の平均気温上昇を2℃未満、できれば1.5℃未満に抑えることを目指す」ことが合意されました。
日本の温室効果ガス削減目標は2020年3月30日時点では「2030年度に2013年度比で26%削減する」というものでしたが、2021年4月22-23日に開催された、米国主導で40の国・地域の首脳らが参加した気候変動サミットで、菅総理大臣が「2030年度において2013年度比で46%の削減を目指す」と宣言しました。
BOP(ビー・オー・ピー)
Base Of the Pyramid(ベイス・オブ・ザ・ピラミッド)の略で、BOPまたはBoPと呼びます。
日本語に訳すと「ピラミッドの底辺」となりますが、世界の所得と人口の分布をピラミッドで表した時に、所得が最も低く、かつ多数を占めている層の人達を顧客やビジネスパートナーにするという文脈で、未開拓の市場を開拓するBOPビジネスという意味合いで使われています。
2007年に国際金融公社 (IFC) と世界資源研究所 (WRI) が、購買力平価で年間所得が3,000USドル未満の層をBOPと定義しました。この層に当てはまる人口は2007年当時で約40億人(世界人口の約72%)、市場規模5兆ドルと見積もられています。

以前はBottom Of the Pyramid(ボトム・オブ・ザ・ピラミッド)と呼ばれていましたが、最近ではBase Of the Pyramid(ベイス・オブ・ザ・ピラミッド)と呼ばれる方が主流となっています。言葉の変遷と同じように、「BOPバージョン1.0」では、貧困層を顧客化するといった考え方でしたが、「BOPバージョン2.0」では、相互価値の創造へと意味合いも変化してきています。
ファッション協定(THE FASHION PACT)
2019年8月にフランスのビアリッツで開かれたG7サミットで、欧米を中心とするファッション・テキスタイル企業32社(150ブランド)が署名した協定で、「気候変動(Climate)」「生物多様性(Biodiversity)」「海洋保護(Oceans)」の3つを柱に、共通の実践目標を掲げました。
2021年7月4日現在で71社が参加しており、世界のファッション産業全体のシェアの3分の1を占めるほどになっています。日本からは、2020年12月10日に日本企業として初めて加盟したアシックス(ASICS)1社のみとなっています。(2021年8月3日現在)
フェアトレード
フェアトレード(Fair trade)とは、適正な価格で継続的に取引することを通して、取引上、弱い立場に置かれている開発途上国の農家や小規模生産者・女性などの生活改善と自立を支援する運動のことを指します。オルタナティブ・トレード(alternative trade)とも言います。
発展途上国の自立を促すという運動として、1960年代にヨーロッパから始まりました。
現在では、イギリスやカナダを中心とした欧米ではフェアトレード認証製品の販売や利用を促進している街を認定する「フェアトレード・タウン」制度が広がっているほか、スターバックスに代表されるような一般の企業も参入しています。
日本では熊本市が2011年に日本初のフェアトレードタウンに認定されました。その後は、名古屋市、逗子市、浜松市、札幌市、いなべ市といった都市が続いています。
ブルーエコノミー
水産業、海運、海洋レジャー、洋上風力発電、海水淡水化、海底地下資源などの海洋に関連する経済活動のことです。雇用、収入、成長を生み出す機会を利用するだけでなく、海洋資源を持続可能な状態に維持するための保護や回復といった活動のことも含みます。
ブルーエコノミーの概念は、2012年の国連における持続可能な開発会議で、環境配慮型の経済を「グリーンエコノミー」と呼び、一方で、海洋環境の保全と持続可能な利用を通じた経済を「ブルーエコノミー」と呼んで、陸地面積や人口は小さいものの、広大な排他的経済水域(EEZ)を有している島嶼国の経済振興支援を訴えたことが始まりとされています。
経済協力開発機構(OECD)が発表した『2030年の海洋経済』によると、世界経済に対する海洋の貢献は、2010年と比較して2030年までに2倍の3兆米ドル(330兆円)に達し、約4,000万人にフルタイムの雇用を提供すると予想されています。
ブルーカーボン
海藻・海草・湿地・干潟・マングローブ林などの海洋生態系によって隔離・貯留される炭素のことをブルーカーボンといいます。
国連気候変動枠組条約(UNFCC)によると、陸域及び沿岸生態系の保護・回復・持続可能な管理は、世界の平均気温上昇を2℃未満に抑えこむ解決策のなかで最大37%を占める重要な手段とされています。
ベーシックインカム
ベーシックインカム(basic income)とは、政府が全国民に対して最低限度の生活を保障するために現金を支給する政策のことをいいます。 頭文字をとってBIと呼んだりもします。
生活保護や失業保険、子育て養育給付などの現金給付政策をBI(ベーシックインカム)と表現することもあり、無条件で国民に現金を給付する政策はそれと区別するためユニバーサルベーシックインカム(Universal Basic Income)、頭文字をとってUBIと表現されることもあります。
MaaS(モビリティ・アズ・ア・サービス)
「情報通信技術を活用することによって、自家用車・タクシー・バス・鉄道・航空・海運等の様々な交通手段による移動をクラウド化し、公共交通か否か、またその運営主体にかかわらず1つのサービスとして統合されたもの」で、新しい移動の概念といえます。
MaaS実現のためには、パーソナルデータ、運行情報、位置情報、交通情報などの移動・交通に関する大規模なデータをオープン化して連携することが必要となります。
また、サービスの深化には、5GやAI、自動運転などの各種先端テクノロジーの進展レベルが大きく関わってきます。
リカレント教育(リスキリング)
人生100年時代といわれるなか、定年後も新しい仕事に就いたり起業したりといったように、学び方や働き方が変化しています。
学校教育を終えた社会人が職業能力の向上につながる高度な知識・技術や教養を身につけるために、生涯に渡って繰り返し学習する「リカレント教育」や、デジタル化と同時に生まれる新しい職業につくためのスキル習得に取り組む「リスキリング」への取り組みが求められています。
リバース・イノベーション(Reverse innovation)
リバース・イノベーションとは、先進国の企業が、新興国や開発途上国の現地のニーズを基にしてゼロから開発した製品を、自国の市場に展開させるという経営戦略のことを指します。別名、トリクルアップイノベーション(trickle-up innovation)とも呼ばれています。
通常は、先進国の企業が自国で開発して展開した製品をマイナーチェンジしたり、廉価版を作るなどして新興国や開発途上国に展開しますが、この順序を逆転(= reverse)させることからこのように呼ばれます。
GEの成功事例を基に、アメリカのダートマス大学タック・スクール・オブ・ビジネスのビジャイ・ゴビンダラジャン教授とクリス・トリンブル教授が命名しました。GEは電力インフラが不安定な新興国で使用可能、かつ入手可能な価格帯の電池式心電計を開発して展開し、その後アメリカでもウルトラポータブル心電計として販売しています。
従来型のグローカリゼーション戦略ではBOP層を取り込めない、そして破壊的イノベーションで台頭する新興国企業に勝つことができない、といったことがリバース・イノベーションが注目される背景となっています。
おわりに|社会問題の解決策 様々な取り組みやコンセプト一覧
社会問題解決に向けた取り組みは他にも沢山存在していますが、ここで紹介した情報が読者の皆様の暮らし方を考え、行動するためのキッカケの一つになれば幸いです。
また、当サイトでは社会課題をビジネスで解決すべく取り組んでいる企業を数多く紹介しています。
そのなかでも特に注目しているベンチャー企業を中心に一覧にして紹介します。ソーシャルビジネスや社会課題を解決する仕事に就きたいという方にお勧めの情報となっていますので、就職活動・転職活動の情報収集の一環として是非ご覧ください。