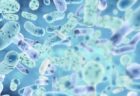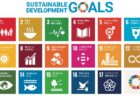人類の発明は自然や生物から着想を得たものが少なくありません。現在、二酸化炭素を原料とした製品を作ることで二酸化炭素を減らす、という活気的な技術開発が進んでいます。それらは植物の光合成やサンゴ礁が石灰質の骨格を形成するプロセスに学んでいます。
本稿では、そのようにして、自然や生物を模倣することでイノベーションを生み出す「バイオミミクリー(バイオミメティクス)」について紹介します。生物多様性から得られる恵みを意味する「生態系サービス」の4つの機能のうち「供給サービス」に該当するものです。
目次
バイオミミクリー(バイオミメティクス)とは
「バイオミミクリー」(英語: biomimicry)とは、自然や生物の優れた形・構造・機能などから学び、模倣することによって持続可能な技術を開発するデザイン手法のことを意味しています。1997年に『自然と生体に学ぶバイオミミクリー』(原題: Innovation Inspired by Nature)を出版した、ジャニン・ベニュス氏が名付け親と言われています。日本語では「生物模倣」と訳されています。
「バイオミメティクス」とも呼ばれます。こちらの方が歴史は古く、1950年代に米国のオットー・シュミット博士が、ギリシャ語の”bios”(英語: life) と”mimesis” (英語: imitate)を結びつけて、生物学から発想したアイデアを工学に転換する技術を「バイオミメティクス」(英語: biomimetics)と名付けました。
人間が科学知識を積み上げて開発するだけでは限界があるため、35億年かけて生存競争や環境変化を生き抜いてきた生物が持つ機能・原理・システムを観察・分析し、模倣することによって飛躍的なイノベーションを狙う取り組みです。
バイオミミクリーは現代の地球環境問題を解決する可能性を秘めており、国連も注目しています。国連環境計画はこのコンセプトの提唱者であるジャニン・ベニュスを表彰し、優れたバイオミミクリー関連技術を紹介するプロジェクト「Nature’s Best 100」を実施しています。
ジャニン・ベニュス氏は、2006年に公式の教育施設や美術館や自然センターにバイオミミクリーを導入する非営利機関を共同で設立し、100を超える大学がバイオミミクリー教育者ネットワークとなって生物学の授業を行っています。2008年には、AskNature.orgというサイトを立ち上げ、2010年には「バイオミミクリー3.8」を創業し、コンサルティング、人材訓練、教育カリキュラムの開発などを行っています。
ファーマニアン経営経済研究所(FBEI)は、2011年8月、バイオミメティクスの活動を数字で示す手段として「ダヴィンチ指数」を発表しました。同指数によれば、2000年から2010 年にかけて、バイオミメティクスの活動は 7.5倍以上に拡大(年率成長率22%)し、バイオミメティクスに関する学術論文は5倍に増え、生物模倣のデザイン研究に対する助成金は4倍に増えて9300億ドルに達したとのことです。
この分野ではドイツが先行しており、2001年には政府主導で28の研究組織からなる「BIOKON」が設立され、バイオミメティクスの産業展開推進機能を担っています。2011年には世界初のバイオミメティクスに関する国際見本市を開催しました。
米国では、NSF(米国国立科学財団)やDARPA(米国国防高等研究計画局)によって研究開発に対する助成が行われています。米カリフォルニア州サンディエゴはバイオミメティクスに特化した開発拠点都市になることを公約しており、2015年3月にはサンディエゴでバイオミメティクスに関する国際会議を開催しました。
バイオミミクリーの事例
レオナルド・ダ・ヴィンチが、飛ぶ鳥を長年観察した結果に基づいて、空を飛ぶハングライダーやヘリコプターなど多くの機械を設計したり、現代の薬に使われている化合物のうち7000種以上が植物に由来するなど、バイオミミクリーの歴史は長く事例も膨大です。
ここでは、人類が直面する大きな危機である「地球温暖化」の原因である、大気中の二酸化炭素を削減する可能性をもつ2つの技術事例を紹介します。
植物の光合成に学ぶ
植物は、太陽光のエネルギーを使って水と二酸化炭素からデンプンなどの有機物と酸素を作り出す「光合成」を行います。この「光合成」のプロセスを真似て、太陽光で水を分解することで水素を作り出し、その水素と二酸化炭素を反応させて有用な物質を合成することが「人工光合成」です。
「人工光合成」が実現すると、これまでは物質を作るために使用していた二酸化炭素の使用量が減少するだけでなく、材料として使うことで二酸化炭素を削減することができるようになります。
日本では信州大学(長野県松本市)の堂免一成特別特任教授が、酸化亜鉛などを使った微粒子状の光触媒を開発し、太陽光のみを使って水から直接水素を作り出すシステムを構築しました。2026年を目指して長野県飯田市に世界最大級の約5000平方メートルの実証施設を計画中です。
また、三菱ケミカルが人工光合成でプラスチック等の化学品原料となるオレフィンを作り出す研究開発を進めており、2030年にかけて大規模な実証実験を行い、その後、2050年までの早い時期での大型商用化プロセスの建設を目指しています。
サンゴ礁の造礁機能に学ぶ
海の中に生息する造礁サンゴは、石灰質の石の骨格を自らの下につくる機能を持っています。この石はサンゴの成長と共に大きくなり、テーブル状、枝状、キャベツ状など、環境に応じた形体となり、長い年月をかけてサンゴ礁といわれる地形をつくります。
サンゴ礁が二酸化炭素を取り込んで石灰岩化する機能から学ぶことで、セメントを製造するプロセスにおいても、二酸化炭素を材料とする炭酸カルシウムを用いてコンクリートを製造するという研究開発が進んでいます。
全世界でセメントは年間45億t(2015 年時点)生産されており、1tのセメントをつくるのに、約800kgの二酸化炭素が排出されています。現在までの人類の活動由来の排出量のうちの5%がセメント生産によるものと言われいますので、この技術はカーボンニュートラルの実現に多大な貢献をすることになるでしょう。
モルフォ蝶の特徴的な羽の色に学ぶ
中南米に生息するモルフォ蝶は特徴的な青色の羽から「生きた宝石」と呼ばれています。羽そのものは特定の色を持たず、鱗粉の積層構造が青色の波長だけを強く反射することで、独自の青色を出しています。
その羽の発色原理を「構造発色」といいます。色素を使わずに発色するため、紫外線による脱色や重金属の使用が不要で、環境にやさしい色として利用されています。繊維や自動車の塗装、ディスプレイなど、さまざまな分野で応用されています。
構造発色繊維モルフォテックスは、染色することなく、その構造によって光を干渉させ発色する画期的な繊維です。また、色をつけていないため、色があせるということがありません。繊維をそのまま織り込んだり、細かく裁断して樹脂に混ぜたりして製品になります。衣料品や家庭用品、化粧品等に使われています。
ヤモリの足の裏の構造に学ぶ
ヤモリの足裏にはナノメートルサイズの毛がびっしりと生えており、この毛先が壁の凹凸に追従することで、ファンデルワールス力という分子間引力を発生させています。この力を利用してヤモリは壁や天井にくっつくことができます。そのヤモリの足の裏の構造を参考にしたテープが開発されています。
日東電工が大阪大学中山研究室と共同開発した「ヤモリテープ」は、カーボンナノチューブ(CNT)を用いて繊維構造体を作製し、ヤモリに近いせん断接着力を実現した人工粘着テープです。
信越化学が開発した「シャイングリップ」は、接着物の表面にナノスケールの微細なマッシュルーム形状の凸構造を形成し、ファンデルワールス力を発生させて接着させる仕組みとなっています。
おわりに|バイオミミクリー(バイオミメティクス)とは?
気候変動や資源枯渇などの大きな課題に直面する人類は、その解決の可能性を秘めたバイオミミクリーの学びの源泉である「生物(の多様性)」が急速に失われつつあります。SDGsの基礎となった概念である「プラネタリー・バウンダリー(一線を超えてしまうと、元に戻れない上に、急激に環境が変化する危険性があるある境界線)」においても、絶滅速度は危機的領域に達しています。
一旦失われてしまった種は元には戻りません。「将来の可能性の種」を自ら消し去ってしまわないためにも、生物多様性の維持にもっと力を入れる必要があります。
参考文献:
•TED ジャニン・ベニュス: 行動するバイオミミクリー
•TBR 産業経済の論点 バイオミメティクスの新展開 ~生物に学ぶものづくりイノベーションの現状と課題~ 増田 貴司 東レ経営研究所 産業経済調査部門長 チーフエコノミスト
•Cnet Japan バイオミミクリー–自然に学ぶインダストリアルデザイン