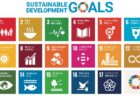最近ではサステナビリティへの注目が高まっていますが、1970年代にサステナブルな暮らし方を提唱してきた「パーマカルチャー」という思想・方法があります。
農を中心に、暮らし方全体のデザイン方法を提唱する「パーマカルチャー」について、そのルーツや原則、手法の事例について紹介します。
目次
パーマカルチャーとは
「パーマカルチャー」(英語:Permaculture)とは、「永続性」を意味する “Permanent”、「農業」を意味する “Agriculture”、「文化」を意味する”Culture” の3つを組み合わせてできた言葉です。
1970年代にオーストラリア南部のタスマニア島で暮らしていたビル・モリソン氏とデイヴィッド・ホルムグレン氏が提唱したのがパーマカルチャーの始まりです。それ以来、世界各国に広がり実践されています。
永続可能な農業をもとに、人と自然が共に豊かになれるような関係を築いていくためのデザイン手法のことを示しています。デザインの対象となるのは、農業だけでなく、植物や動物、建物やコミュニティなどの生活すべてに及びます。
一見、パーマカルチャー農園のイメージが強いため「パーマカルチャー」=「農業」と認識されがちですが、農業だけでなく暮らし方全般をデザインしていく思想となっています。
「世界中を森にすることで世界に広がる森をつくり、森が与えてくれるものを食べる、そして人間以外の生き物たちとの共存を目指す。」というのがパーマカルチャーの目指している世界観となります。
森でできた季節折々の素材の食材を活かす料理を楽しむ、捨てる前にもったいないものを活かせる方法はないか考える、もともとここにある資源を最大限活かす、など、我々の暮らしに取り入れる方法はたくさんあります。環境問題が深刻化してきている今だからこそ、このパーマカルチャーの考えから学ぶべきところがたくさんあると注目されているのです。
パーマカルチャーの3つの倫理と12の原則とは
パーマカルチャーにおいての3つの倫理が示されています。倫理とは、自らの自由を実践するために自らに課す行動基準のことです。
| 【パーマカルチャーの3つの倫理】 |
|
地球への配慮は、わたしたちの大切な森を守ることにつながります。無限なる命を生み出す森を守り共に育てていくことが地球への最大の配慮になるのです。
人と自然が共存する中で、お互いに助け合い恵みを分かち合うことによって生活の安定や心の安心感が生まれます。ひとりひとりが持つ個性や才能を、自分のためだけではなく他人や社会全体へと用いることでより豊かな社会へと導いていけるでしょう。
加えて12のデザイン原則を提唱しています。これは3つの倫理を基準に、パーマカルチャーの創始者であるデイヴィッド氏によって、具体的なアクションとして示されました。
| 【パーマカルチャーの12のデザイン原則】 |
|
パーマカルチャーの具体的な手法例
パーマカルチャーの手法の例をいくつか紹介します。
コンパニオンプランツ
「コンパニオンプランツ」とよばれる植物の組み合わせを利用した手法があります。一緒に作ると互いに良い影響を与え合う相性の良い植物の組み合わせのことで「共栄作物」とも呼ばれています。
自然資源の利用方法のひとつで、長年の経験で培った知識や工夫を重ねた手法で植物の力を借りて人の手間を省くことができます。
コンパニオンプランツで大切なのは、土の質の良さ、空間の取り方、生態系のバランスです。自然の生態系を活かすということは、自然とわたしたちの生活どちらにも有意義なことだといえるでしょう。
チキントラクター
エコで自然にやさしい草刈り機と呼ばれている「チキントラクター」もパーマカルチャーの手法のひとつです。
チキントラクターは、移動式の鶏小屋のようなもので、ニワトリはこのチキントラクターの中の地面に生えている草を食べます。移動しながらニワトリが草を食べてくれるのでエネルギーいらずの草刈り機の役割を果たしてくれるのです。
雑草や害虫を食べてくれるので減農薬にも役に立ちます。鶏のフンも肥料となり活用できるので環境にやさしい循環型農業といえます。
ニワトリの飼育は大型の畜産動物よりも扱いやすく低資金でも始めやすいという特徴があります。
アースオーブン
「アースオーブン」とよばれる土でできたドーム型のオーブンがあります。土と砂があればどこでも簡単につくることができるので、古くからアメリカ大陸や中東などで使われていた歴史があります。
コンポスト
都会に暮らしている人であれば、コンポストが取り入れやすい手法でしょう。コンポストとは、生ゴミや雑草を利用して堆肥をつくることを意味します。生ゴミの排出量を減らすことや環境保護にもつながります。
日本におけるパーマカルチャー実践者の例
日本各地で行われているパーマカルチャーを実践している人たちの実例です。
パーマカルチャー研究所(北海道)
 ▼運営サイト: パーマカルチャー研究所
▼運営サイト: パーマカルチャー研究所
北海道大学工学部出身で電力・エネルギーを専門に学び、東京電力に勤務するも、需要がある限り電気を作り続けるのが仕事に疑問を感じて退職。
タイ・ラオス国境の山岳地帯にあるパーマカルチャーファーム「サハイナン」に3ヶ月間滞在し、エネルギーを使わない不便さよりも使わないからこそのスローで豊かな生活を実感。2016年に「パーマカルチャー研究所」として北海道札幌市の山奥で、遊びと暮らしと仕事と学びが一体化した、「遊暮働学(ゆうぼどうがく)」の自給自足的ライフスタイルを実践しながら情報を発信しています。
富士エコパークビレッジ(山梨県)
 ▼運営サイト: 富士エコパークビレッジ
▼運営サイト: 富士エコパークビレッジ
富士エコキャンプ場は2001年以来体験型の環境教育施設として発足。オーストラリアのパーマカルチャーの理念のもとに、地球にやさしい暮らし方を提案しています。畑では農薬や化学肥料を全く使用しない野菜作りに取り組んでいます。
キャンプ場は循環型の暮らしを体験できる施設で、電気はすべて太陽光や風力、そしてバイオマスなどの自然エネルギーで自給しています。
パーマカルチャーセンタージャパン(神奈川県)
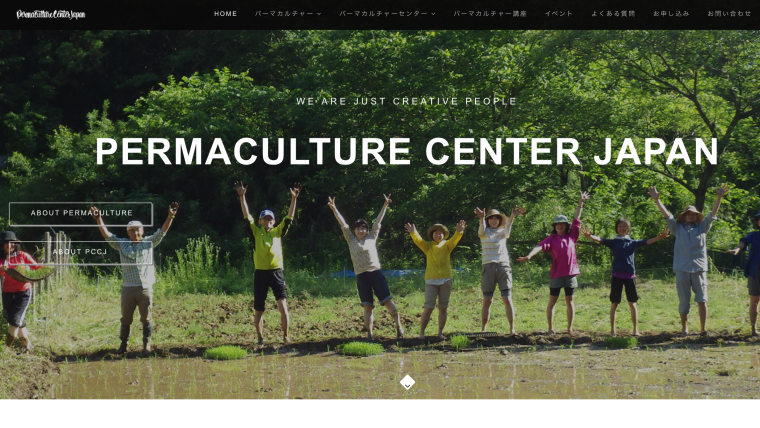 ▼運営サイト: パーマカルチャーセンタージャパン
▼運営サイト: パーマカルチャーセンタージャパン
1996年に神奈川県相模原市に設立された施設です。日本では唯一、「パーマカルチャーデザイナー」という資格を取得することができる施設となっています。
パーマカルチャー講座やパーマカルチャーフェスなど、様々な講座やイベントを企画・運営しながら、パーマカルチャーの普及に努めています。講座では、「農場づくり」「米と野菜作り」「アースバッグハウスづくり」といったことを年間を通じて実践しつつ、野草の使い方を学んだり、ソーラードライヤーやロケットストーブづくりなどを体験したりできます。
おわりに|パーマカルチャーとは
50年の時を経て、パーマカルチャーという言葉が再び、サステナビリティに対する関心が高い人達の間で注目を集めつつあります。
パーマカルチャーをコアに実践している人からは、ややもすれば原始的で世間からは隔絶された暮らしをしている印象を受けることもあり、一般人にとっては敷居の高さを感じさせるところがあります。しかし、普通に暮らしている多くの人たちが、テクノロジーの活用も含めて、生活の中にパーマカルチャーの思想や方法論を上手に取り入れていくことが、世界のサステナビリティを高めていくためのポイントとなっています。