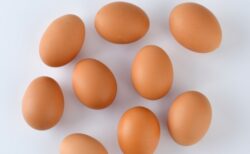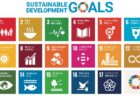日本は世界で第4位のコーヒー消費国で、カフェや自宅以外にコンビニでも手軽に飲めるほどコーヒーが浸透しています。同時に、コーヒーを抽出した後に残るかす(コーヒーグラウンズ)が大量に発生し、廃棄されているという現実があります。
この記事では、コーヒーかすの廃棄状況と、コーヒーかすの再利用に挑む企業の取り組みやアップサイクル事例を紹介します。
目次
コーヒーかすの廃棄問題
全日本コーヒー協会の発表によると、2020年時点における日本国内のコーヒーの消費量は約43万トンとなっています。抽出後のコーヒーかすは含水率が65以上と、かすの重さ以上の水分が含まれるため、単純に倍としても重量ベースで約86万トンのコーヒーかすが発生していることになります。
この水分を含んだコーヒーかすを処分するためには、膨大な焼却エネルギーや埋め立て処分場が必要になります。更に、長時間放置して腐敗が進むと温室効果の高いメタンガスを発生させてしまうことも問題視されています。
令和2年度における国内のごみ焼却施設数は1,056基で世界一となっており、燃やして処理するごみの量も世界で最多となっています。
多くの自治体で「燃えるごみ」「燃やすごみ」と呼んでいるごみの、40%前後が生ごみとなっています。この生ごみの重量のうち80〜90%が水分となっているため、生ごみを燃やすのは水を燃やすのに等しい行為といえます。また、焼却によってごみを減量しているにも関わらず、最終処分場の受け入れ可能な容量は逼迫しています。
コーヒーかすを飼料・肥料・バイオ燃料に利用
日本では、コーヒー豆の輸入・加工事業者や、カフェチェーンなどの大手企業が中心となって抽出後のコーヒーかすの有効活用を進めています。ここでは、コーヒーかすを飼料・肥料・バイオ燃料に利用している事例を紹介します。
コーヒーかすを利用した飼料
コンタクトレンズメーカーの株式会社メニコンが、発酵促進技術を応用することで、コーヒーかすを飼料として利用可能にする技術を実用化することに成功しました。これによって、本来はゴミであったコーヒーかすが以下のような効果を生み出しています。
①乳品質の向上と乳出荷量の増加
コーヒーかすに含まれる生理活性物質(抗酸化成分等)が含まれた飼料を乳牛に給餌した際、乳品質が向上するとともに乳出荷量が増えました。また、牛の病気である乳房炎を抑制するために投与する抗生物質を半減できた例も多くあります。
②牛のゲップによるメタンガス抑制
牛1頭の体内から1日5ℓのメタンガスがゲップにより放出されていますが、当該飼料を給餌した場合、体内からのメタンガスを50~70%削減できる可能性が示唆されました。
③リサイクルループの構築
スターバックスの店舗で排出されたコーヒーかすを飼料として活用し、牛から絞ったミルクを店舗で利用するというリサイクルループを確立しました。
コーヒーかすを利用した培地や堆肥
神奈川県農業技術センターでは、キノコ廃培地や野菜屑などとコーヒーかすを混ぜて堆肥化する方法を検証しました。
- エリンギィの培地としてコーヒーかすに米糠と廃培地を容量比で1:1:1で混合した培地で実用化が可能
- 細かくスライスしたスイカにコーヒーかすとコーンの茎や葉を混ぜ合わせた結果、悪臭を発生させない肥料が生成され、コマツナ栽培に有用と判明
- 窒素成分を多く含むものの、分解に伴い水分や悪臭が発生しやすく、単品では堆肥化は困難なオカラにコーヒーかすを副資材とすると良好な堆肥が作成できることが判明
といった良好な結果を得ることができました。
また、コーヒー豆の輸入・加工・販売大手のUCC上島珈琲株式会社は、近畿大学農学部との共同研究結果を発表し論文として公表しています。この研究結果からも、コーヒーかすは有機質資材として農耕地へ投入できることが明らかにされています。
コーヒーかすを利用したバイオ燃料
コーヒー豆輸入商社の石光商事株式会社(兵庫県神戸市)は、近畿大学(大阪府東大阪市)と、コーヒー抽出後に出るコーヒーかすからバイオ燃料「バイオコークス」を製造し、それを燃料として焙煎した環境にやさしいコーヒーを産学連携で共同開発しました。
バイオコークスとは、バイオマス(再生可能な、生物由来の有機性資源)を原料として製造する固形燃料で、2005年に、近畿大学バイオコークス研究所所長の井田民男氏が開発しました。
光合成を行う植物資源等を100%原料にしているため、CO2排出量ゼロで環境に配慮したエネルギーとして期待されています。
コーヒーかすのアップサイクル事例
アップサイクルとは「捨てられるものに価値を付加して新しく別のものに生まれ変わらせること」を意味しています。「創造的再利用」とも呼ばれ、アイデアやデザインが重要な役割を果たすといわれています。
コーヒー業界でも、抽出後のコーヒーかすや焙煎時に選別した欠点豆などを使ってさまざまなアイテムにアップサイクルする事例がでてきています。おしゃれで機能的かつ環境に配慮したコーヒーかすアップサイクル商品を紹介します。
コーヒー粉から抽出したグルテンフリーの小麦代替粉末
 デンマーク発のKaffe Buenoは、コーヒーの粉から脂質を抽出し、それらを標準的な小麦粉の粒子サイズに一致するように滅菌および粉砕した粉末を製造。
デンマーク発のKaffe Buenoは、コーヒーの粉から脂質を抽出し、それらを標準的な小麦粉の粒子サイズに一致するように滅菌および粉砕した粉末を製造。
ベーカリー・菓子・ピザとパスタ・健康的なスナックバーの材料等として販売するとともに、抽出オイルをスキンケア化粧品の原料や飲料の香料・保存料としても製造・販売しています。
コーヒーかすとリサイクルプラスチックから作ったアパレル製品
 フィンランドのスタートアップRensは、コーヒーかすとリサイクルプラスチックから糸(Coffee yarn)を開発し、トレーナーやスニーカーなどのアパレル製品を製造販売しています。
フィンランドのスタートアップRensは、コーヒーかすとリサイクルプラスチックから糸(Coffee yarn)を開発し、トレーナーやスニーカーなどのアパレル製品を製造販売しています。
コーヒーかすを混ぜた糸は消臭効果があり、不快な匂いを吸収するため洗濯回数を減らすことができるとのことです。(同社サイトより)
コーヒーかすを素材に使った陶器調のカップ・ソーサー
 ドイツ(ベルリン)のkaffeeformは、カフェから集めたコーヒーかすに天然由来セルロースの接着剤や粉砕された木材などを組み合わせてコーヒーカップとソーサーを製造販売しています。
ドイツ(ベルリン)のkaffeeformは、カフェから集めたコーヒーかすに天然由来セルロースの接着剤や粉砕された木材などを組み合わせてコーヒーカップとソーサーを製造販売しています。
陶器のような見た目でありながらも、軽くて割れにくいのが特徴です。すべての製造工程を主にベルリンで行っており、他の原料の調達もドイツ国内で完結することで、ローカルの繋がりと輸送時の二酸化炭素排出抑制を実現しています。
コーヒーかすを釉薬として使用した磁器のペンダントランプ
 中国(上海)のCOFFIREは、コーヒーかすを着色材料として使い、大理石のテクスチャを施すという新しい磁器の表面仕上げ技術を用いたペンダントランプを制作しています。
中国(上海)のCOFFIREは、コーヒーかすを着色材料として使い、大理石のテクスチャを施すという新しい磁器の表面仕上げ技術を用いたペンダントランプを制作しています。
ピンクの大理石のような表面の質感となっており、従来の釉薬では実現できないような効果が得られるとのことです。
コーヒーかすを配合した素材で作られたインテリアグッズ
 日本(神奈川県)の株式会社コルは、抽出後のコーヒーかすを配合して固めたアップサイクル素材『COFFEE STONE(コーヒーストーン)』を用いたアクセサリー類や、キャンドルホルダー等のインテリアグッズを製造販売しています。
日本(神奈川県)の株式会社コルは、抽出後のコーヒーかすを配合して固めたアップサイクル素材『COFFEE STONE(コーヒーストーン)』を用いたアクセサリー類や、キャンドルホルダー等のインテリアグッズを製造販売しています。
海水由来の自然素材を主材料とし、捨てられてしまう抽出後のコーヒーかすを20~30%ほど配合して固めた素材(石油由来の化学物質不使用)で、コーヒーの色合いと粒の風合いが感じられ、石のような質感となっています。
コーヒーかすを使用した石鹸や入浴剤などのバスグッズ
 日本(北海道)の北海道コカ・コーラボトリングが、自社の札幌工場から出るコーヒー豆かすを、石鹸や入浴剤などのバスグッズ商品としてアップサイクルしています。
日本(北海道)の北海道コカ・コーラボトリングが、自社の札幌工場から出るコーヒー豆かすを、石鹸や入浴剤などのバスグッズ商品としてアップサイクルしています。
石鹸はコールドプロセス製法によって、原料の 植物油に含まれるオレイン酸などの保湿成分を損なうことなく、しっとりとした洗い心地の優しい石鹸に仕上げています。バスシュガーは砂糖をベースに作られた入浴剤で、肌に水分をキープして湯上りの乾燥を防ぎます。
UP COFFEE CHALLENGE
 アップサイクルでコーヒー産業をサステナブルにすることを目指す複数の企業やカフェが集まって、コーヒー豆かすをアップサイクルしたり、カスカラ(生産国で廃棄されているコーヒーの果皮の部分)の有効利用を促進する『UP COFFEE CHALLENGE』という活動を行なっています。
アップサイクルでコーヒー産業をサステナブルにすることを目指す複数の企業やカフェが集まって、コーヒー豆かすをアップサイクルしたり、カスカラ(生産国で廃棄されているコーヒーの果皮の部分)の有効利用を促進する『UP COFFEE CHALLENGE』という活動を行なっています。
キッチンアイテムやバスグッズなど、コーヒーかすを使った様々なアップサイクル商品の開発に取り組んでいます。2024年1月には、Cafeや消費者をサポーターとして巻き込んでコーヒー豆かすの循環モデル作りへの挑戦を開始しています。
おわりに|コーヒーの持続可能性向上のためにできること
毎日大量のコーヒーかすが廃棄されているなかで、コーヒーかすを再利用・アップサイクルする取り組みについて紹介しました。
2022年11月25日には、全日本コーヒー協会が、コーヒーを抽出した後のコーヒー粉は、肥料・堆肥、消臭・脱臭剤など様々なものに有効に活用できることから、「コーヒーかす」の呼称を「抽出後のコーヒー粉(コーヒーグラウンズ)」と改め、廃棄物ではなく有効活用できる資源としてのイメージアップと新たな呼称の普及活動に努めていくと発表しました。
天然ガスや飼料、肥料は世界的に奪い合いとなっていることから、コーヒーかすを利用して飼料や肥料をつくることは食料安全保障にも貢献しています。個人でも、コーヒーかすを再利用したりアップサイクルアイテムを購入したりすることは、焼却炉の負担を減らし、温室効果ガスの抑制につながる価値ある行動といえるでしょう。
加えて、自然環境や生産者の生活など、コーヒー産業のサステナビリティ(持続可能性)に配慮して生産されている「サステナブルコーヒー」を選択することが、将来にわたってコーヒーを楽しむために私たちができる大きな貢献の一つとなります。
私たちの家庭で出たコーヒーかすを再利用する方法についてはこちらの記事をご覧ください。