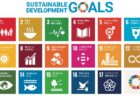「買い物難民」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?さまざまな原因によって買い物が困難となった人を指します。別名、「買い物弱者」ともいわれています。
ここでは買い物難民について詳しく解説するとともに、その定義や問題点、解決策についても紹介していきます。
目次
買い物難民とは?その問題点とは
買い物難民とは、さまざまな理由によって食料や生活に必要なものを買えなくなる人のことです。
ものだけではなく郵便局や病院、役所などでの手続きなど料金を支払って受けられるサービスを受けられなくなることも含まれ、社会問題になっています。
買い物難民は、買い物や生活に関するサービスが受けられないことから人の命にかかわる問題です。
1人暮らしの高齢者の具合が悪くなったにもかかわらず、どこにも行けず誰にも発見されずに死亡してしまった例もあります。また、一番近くのスーパーが自宅から相当距離があり70代の男性や80代の女性は苦労して買い物に出かけていくそうです。
経済産業省『買物弱者・フードデザート問題等の現状及び今後の対策のあり方に関する報告書(抜粋版)』によると、買い物難民は全国で約700万人いると推計されています。
買い物難民は農村や山間部にある小さな集落で起きている問題だと考えられがちですが、それだけではありません。地方の都市をはじめ団地などが多いベッドタウン、大都市でも買い物難民は存在します。
前回の調査より約100万人増えているデータがあることから、これからも買い物難民は増えていくと考えられているのです。
買い物難民が生まれる原因
社会問題にまで発展している買い物難民問題ですが、どのような原因で生まれるのでしょうか?ここからはその原因について紹介していきます。
商店街やスーパーの廃業
買い物難民が生まれてしまう原因の1つに、スーパーの廃業や各商店・商店街の衰退などが挙げられます。住民の徒歩圏内にある商店街やスーパーが無くなってしまうことにより、買い物に行けなくなってしまうのです。
スーパーの廃業は耐震化やバリアフリー化、防火性の向上など住民の要求や法律によって建物への新しい要求に対応しきれずに廃業するケースが多くみられます。
各商店は少子化によって後継ぎがいなく閉店してしまうケースや、客層の変化に対応しきれないなどの理由から、収益が減少して店を閉めるという場合が多いようです。
商店街の衰退は街に進出したショッピングモールや大型スーパーによって商店街全体の売り上げが減少し、シャッター通り化してしまうケースが増えています。また、古い商売の方法から抜け出せず消費者のニーズに合わせられない店舗があり、商店街としての足並みがそろわず商店街全体が衰退していくケースも多くあります。
公共交通機関の衰退などの交通不便
近所にある商店街やスーパーの閉店によって、徒歩や自転車で買い物に行けなくなった高齢者は自宅から離れた大型スーパーなどに買い物に行かなくてはなりません。
車を持っていない人たちは公共交通機関を使って買い物に行くことになります。しかし、山間部や僻地になると公共交通機関の衰退が顕著です。ひどいところになると鉄道どころかバスも走っていないところもあります。そうなると必然的に買い物に行けなくなってしまうのです。また、車を持っている場合でも過疎地におけるガソリンスタンドの減少が進んでいる現実があります。
経済産業省の資源エネルギー庁によると、平成29年3月末時点でガソリンスタンドが3箇所以下の市町村が全国で302箇所もあることがわかりました。
しかも、ガソリンスタンドがまったくない「ゼロ」の市町村も12箇所存在していたそうです。自分の住む町にガソリンスタンドがなかったり少なかったりする場合は、車の買い物も困難となり買い物難民が生まれてしまいます。
住民の高齢化
山間部や過疎地だけではなく大都市でも買い物難民が生まれている原因として、住民の高齢化、いわゆる高齢化社会があります。
高齢になると次第に足腰が弱まり、自転車はおろか歩くのもおっくうになります。若いころには大した距離ではなくても、気づかぬうちにしんどい距離になっていることが多々あるのです。
また、車の運転も高齢になると判断能力が衰え、周囲から止められるようになり、車でも買い物に行けなくなっている現状もあります。
大都市に住んでいても郊外型大型スーパーが進出してきて、街の商店街や小さなスーパーが競争に負けて衰退・閉店してきています。団地やアパートなどに1人で暮らしている高齢者が、大型のスーパーに足を運べなくなっている現状があるのです。
買い物難民の改善策
日本政府はSociety5.0の中で、過疎地に暮らす買い物難民の問題解決に向けて、ドローンによる荷物の配達や、自動運転車を公共輸送手段として用いる等の提案をしています。
官民問わず、買い物難民などの社会課題を解決するために、AIや5Gなどのテクノロジーを活用した新しい「移動の仕組み(MaaS)」や「街作り(CaaS)」を急いでいます。
また、そうした政府と大企業による大きな取り組みだけでなく、各自治体や地元の有志が買い物難民を少しでも改善させるための推進・努力をしています。
まず、宅配サービスの充実です。ネットスーパーだけではなくNPO法人やさまざまな企業などの新しい取り組みが始まっています。
次に移動販売の推進です。移動販売は宅配サービスとは違い、自分の手に取って商品を買うことができます。特に不便な山間部や過疎地にとっては助かるサービスです。
また、交通機関の不便を解消するために自治体ではコミュニティバスの推進もおこなっています。
さらに、各地で地元有志が集まったりボランティアを集めたりして近隣の商店の協力を得て、週1回空き地で青空市を開催するなどしています。
買い物難民問題の解決に挑む注目ビジネス
とくし丸
 ▼運営サイト: とくし丸
▼運営サイト: とくし丸
買い物の楽しさを残しつつ、買い物難民の人たちを支援することを目的とする移動スーパー。買い物だけではく、見守り隊としての役目を果たすことも目指しています。
生鮮食品を含め400品目以上のアイテムを搭載した冷蔵庫付きの軽トラックで、玄関先まで軽トラックで出向き、会話し、買い物をしていただくというサービスとなっています。
全国のスーパーと提携して、個人事業主などの販売パートナーが軽トラックを導入して移動スーパーサービスを実施するビジネスモデルとなっています。
稼働トラック数は2022年1月24日現在、全国47都道府県で949台となっています。
終わりに|買い物難民とは?
買い物ができないことは本当に不便です。しかも、食料を買えないとなると人命にも関わってきます。
できることは限られてきますが近所の人に声がけをして、体調を聞くなど話し相手になるだけでも力になります。買い物難民を少しでも減らして、誰もが暮らしやすい生活環境を作っていきましょう。